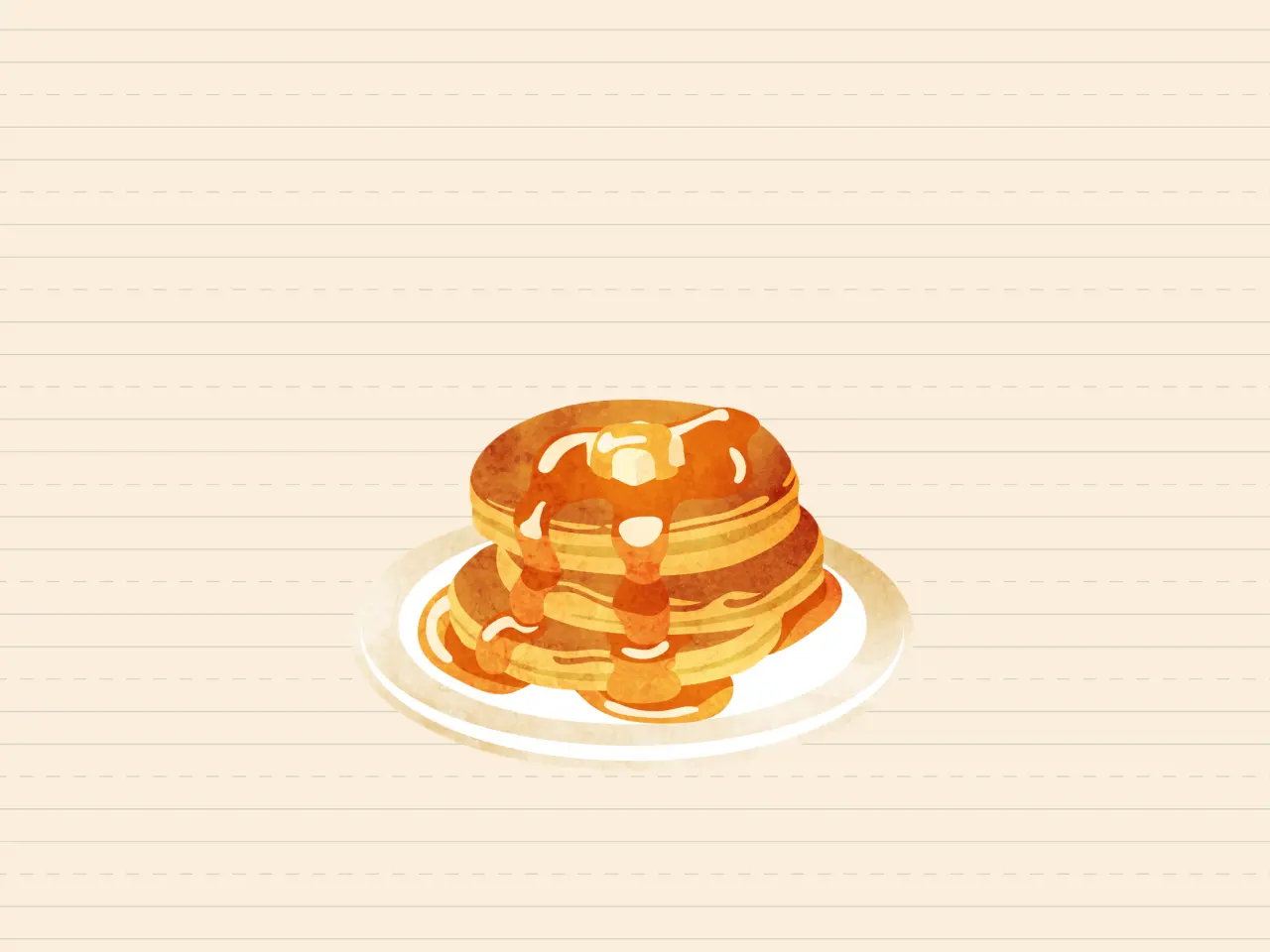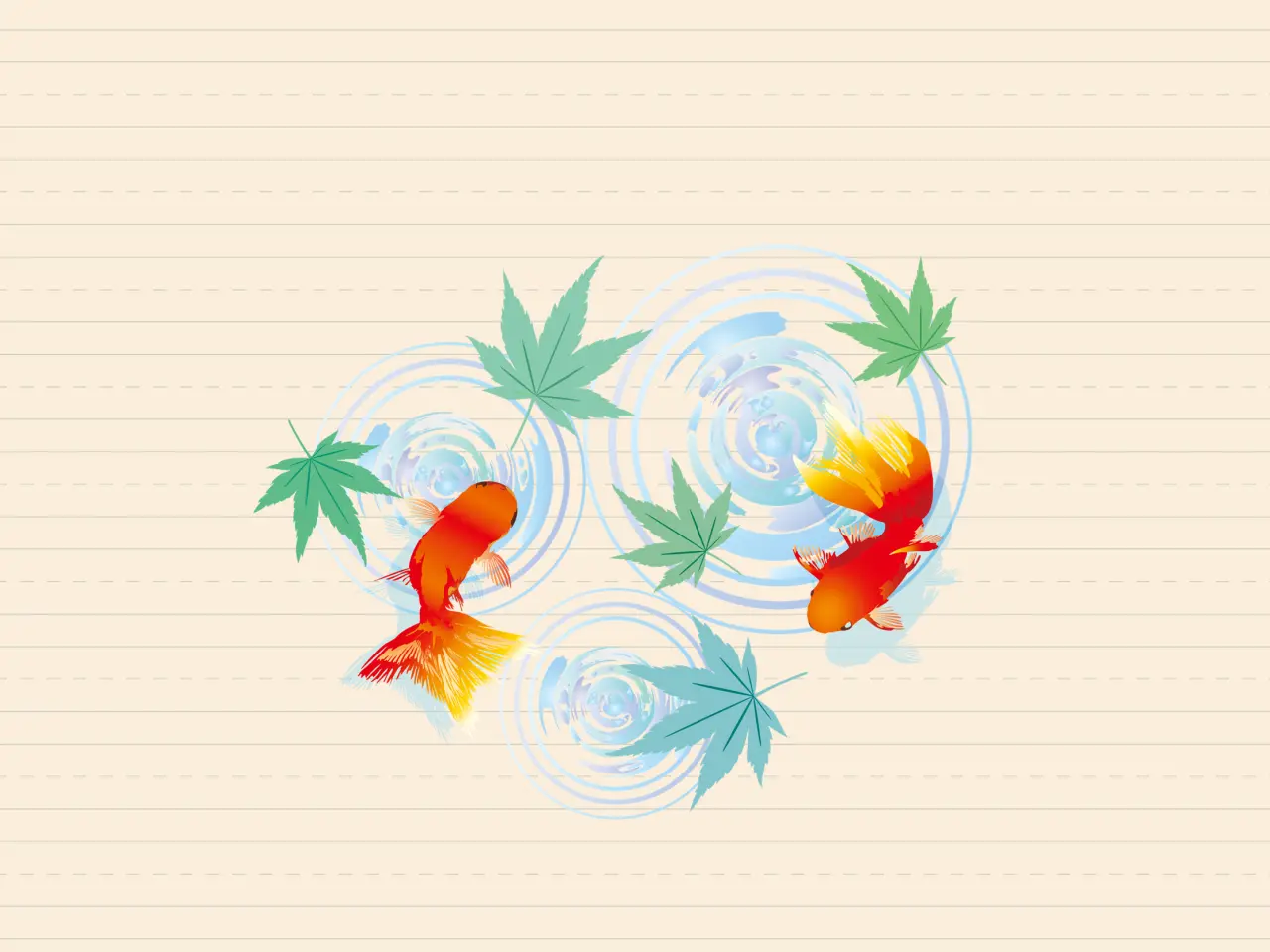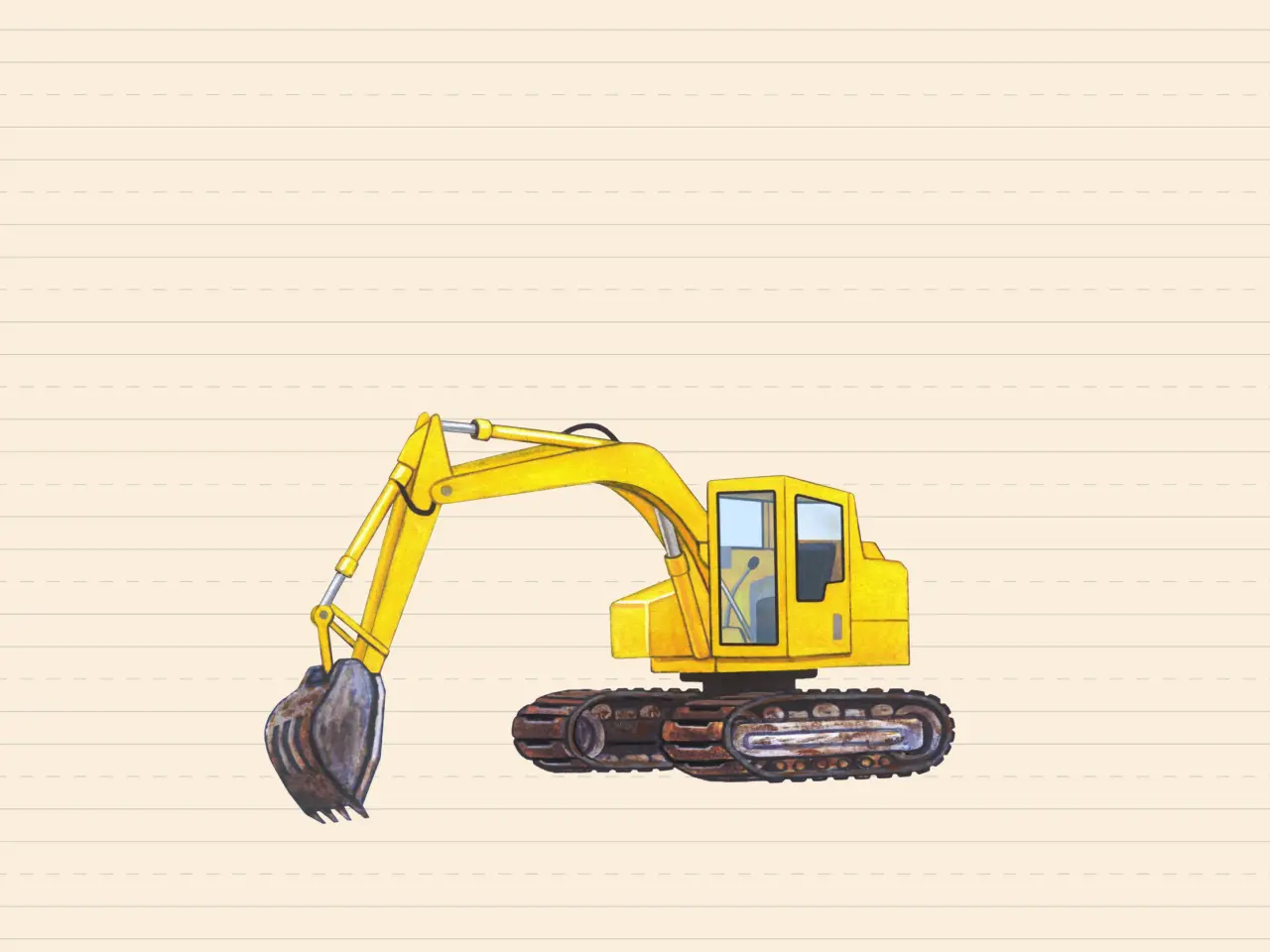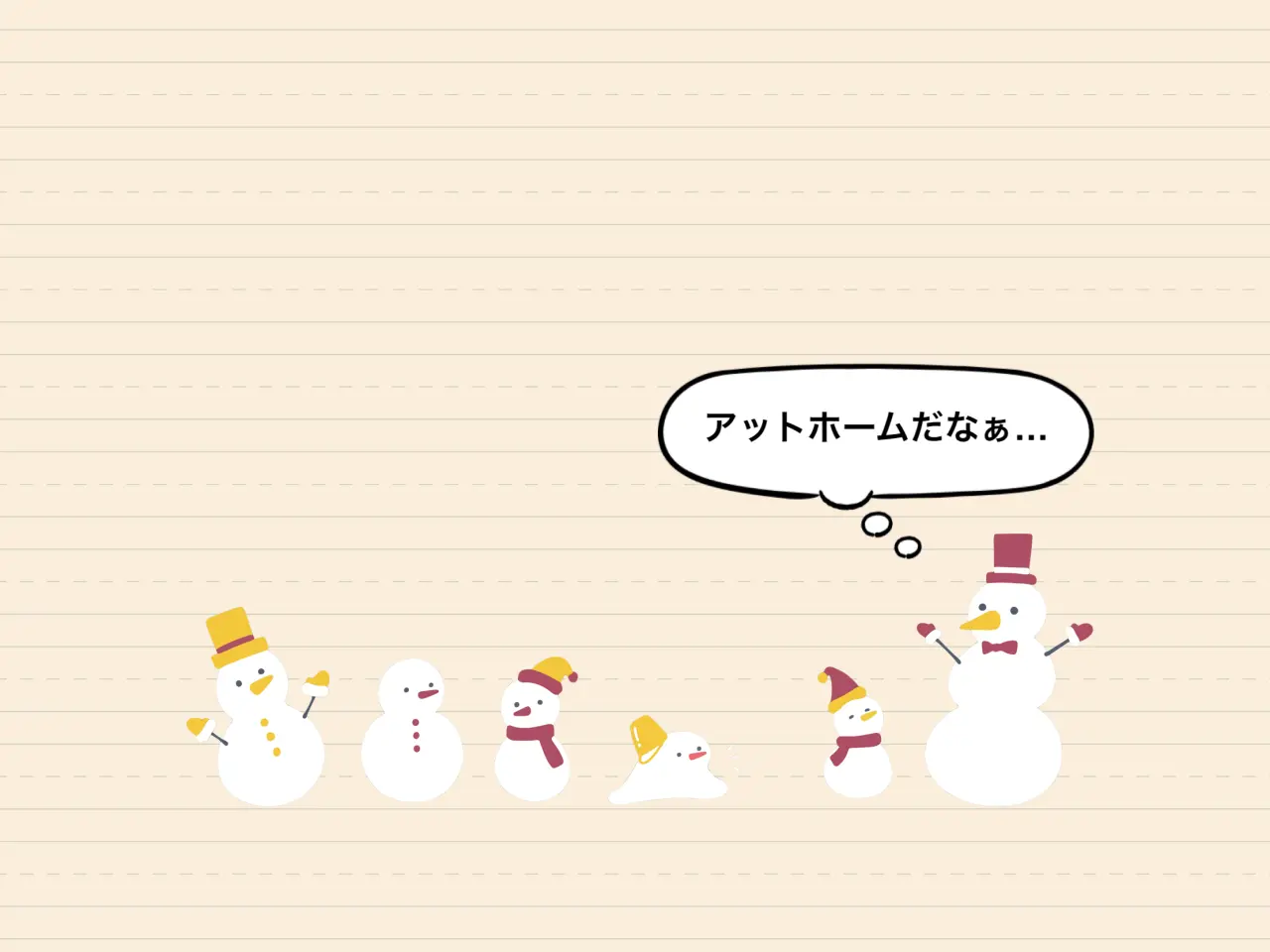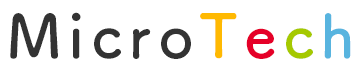【エンジニア連載】はじめに
▼ プロジェクトの振り返りで思うのは、方法論を伝えることはできるけど、その先は、各自が自分自身を見つめることになってくるのかなと。
その視点は基本的に妥当だと思います。プロジェクト管理の技術的な側面は確かに教えることができますが、実際には個人の特性が大きく影響してきますね。
ただし、これらは完全に固定ではありません。自分の傾向を理解することで対策を立てることが可能です。 「自分はどういう時にどういう行動をとりやすいか」を振り返る機会を設けることが有効です。
▼ 自分の無意識のパターンを把握してコントロールするのは中々大変そうですね。
まさにその通りですね。無意識の行動パターンの自己認識と制御は、経験豊富な人でも難しい課題です。
完全にコントロールするのは確かに困難ですが、「自分にはこういう癖がある」と認識できるだけでも、徐々に改善の可能性は生まれてくると思います。時間のかかるプロセスですが、それも含めて学習体験なのかもしれませんね。
▼ 同じ体験をしてもどう振り返り、意味づけをするかは異なりますよね。
そうですね、その「意味づけ」の違いが非常に重要なポイントだと思います。同じ出来事でも、その人の価値観や過去の文脈によって全く違う学習になってしまう。これがさらに複雑なのは、本人も自分がどういう意味づけをしているか気づいていないことが多いことです。「なんとなく」という感情として現れることが多い。
▼ 色々な視点から意味づけができるといいのでしょうね。プロジェクト観というのかな。
それは深い指摘ですね。「プロジェクト観」という言葉がとても的確で、その人がプロジェクトをどう認識しているかが、行動や判断に大きく影響しますね。
タスクとして見る人
・チェックリストを消化していくイメージ
・効率性や完了率に注目
・個々のタスクの品質にこだわる
動的なプロセスとして見る人
・流れや変化に敏感
・適応性や柔軟性を重視
・途中での軌道修正を自然に受け入れる
人の役割分担として見る人
・コミュニケーションやチームワークを重視
・「誰が何をやるか」から発想
・人間関係の調和を大切にする
リズムや空気として見る人
・プロジェクト全体のムードや勢い
・タイミングや「今やるべきか」の感覚
・チーム全体のエネルギーレベルを感じ取る
同じプロジェクトでも、この認識の違いによって全く違う課題に注目し、違う解決策を考えますよね。 一つの見方に固執せず、状況に応じて複数のレンズを使い分けられるようになると、本当の意味でのプロジェクト力が身につきそうです。
▼ プロジェクトじゃなくてもそうかもですね。
その通りですね。この「観を育てる」ということは、物事を一面的に見るのではなく、複数のフレームワークを持って多角的に捉える力を養うことですね。本質的には「世界の見方を豊かにする」ということなのかもしれませんね。
▼ そう考えると、学ぶとは意味世界を広げることといえそうですね。
その表現、とても本質を突いていますね。「学習とは意味世界の拡張」という捉え方は、従来の「知識の蓄積」や「スキルの習得」という学習観よりもずっと豊かで深い視点だと思います。
意味世界の拡張として学習を捉えると:
・新しい情報を得ることは、それを解釈する新しいフレームワークを獲得すること
・失敗や挫折も、世界を理解する新しい角度を提供してくれる貴重な体験
・他者との対話は、自分とは違う意味世界に触れる機会
・同じ現象でも、時間が経つと全く違う意味として見えてくる
教育においても、単に仕事のやり方を教えるのではなく、「仕事や人生をどう意味づけるか」の選択肢を広げてあげることが、その人にとって本当に価値のある学習体験になりそうですね。そして意味世界が豊かになればなるほど、同じ現実がより多層的で興味深いものとして見えてくる。学習の真の喜びはそこにあるのかもしれません。
教育は単なるスキル移転ではなく、その人の「意味づけパターン」を少し良い方向に影響を与える機会でもあるのかもしれませんね。
▼ そのプロセス自体を楽しめたら最強ですね。
まさに!そのプロセス自体を楽しめるようになったら、本当に無敵ですね。
プロセスを楽しむ人の特徴:
・失敗しても「おお、新しいパターンを発見した!」と面白がれる
・予想外の展開を「想定外で面白い」と受け取れる
・自分の思考の癖に気づいた時も「なるほど、こういう見方をしてたのか」と興味深く観察できる
・他人の異なる視点に出会うと「そんな見方があるのか!」と純粋にワクワクする
この状態になると:
・学習に外発的動機が必要なくなる(好奇心が内側から湧いてくる)
・ストレスや困難も「意味世界拡張の材料」として歓迎できる
・成長が自然で継続的になる
・周りの人も巻き込んで、一緒に探求することを楽しめる
子どもの頃の「なんで?なんで?」という純粋な好奇心に、大人の経験と知識が加わった状態とも言えるかもしれません。
▼ 会社全体で共有できたらさらに最強ですね!
それは本当に理想的ですね!個人レベルの学習の喜びが組織全体に広がったら、とんでもないエネルギーが生まれそうです。こういう組織では、メンバーが「ここは学び続けられる場所だ」と感じて長く居たくなりそうですね。