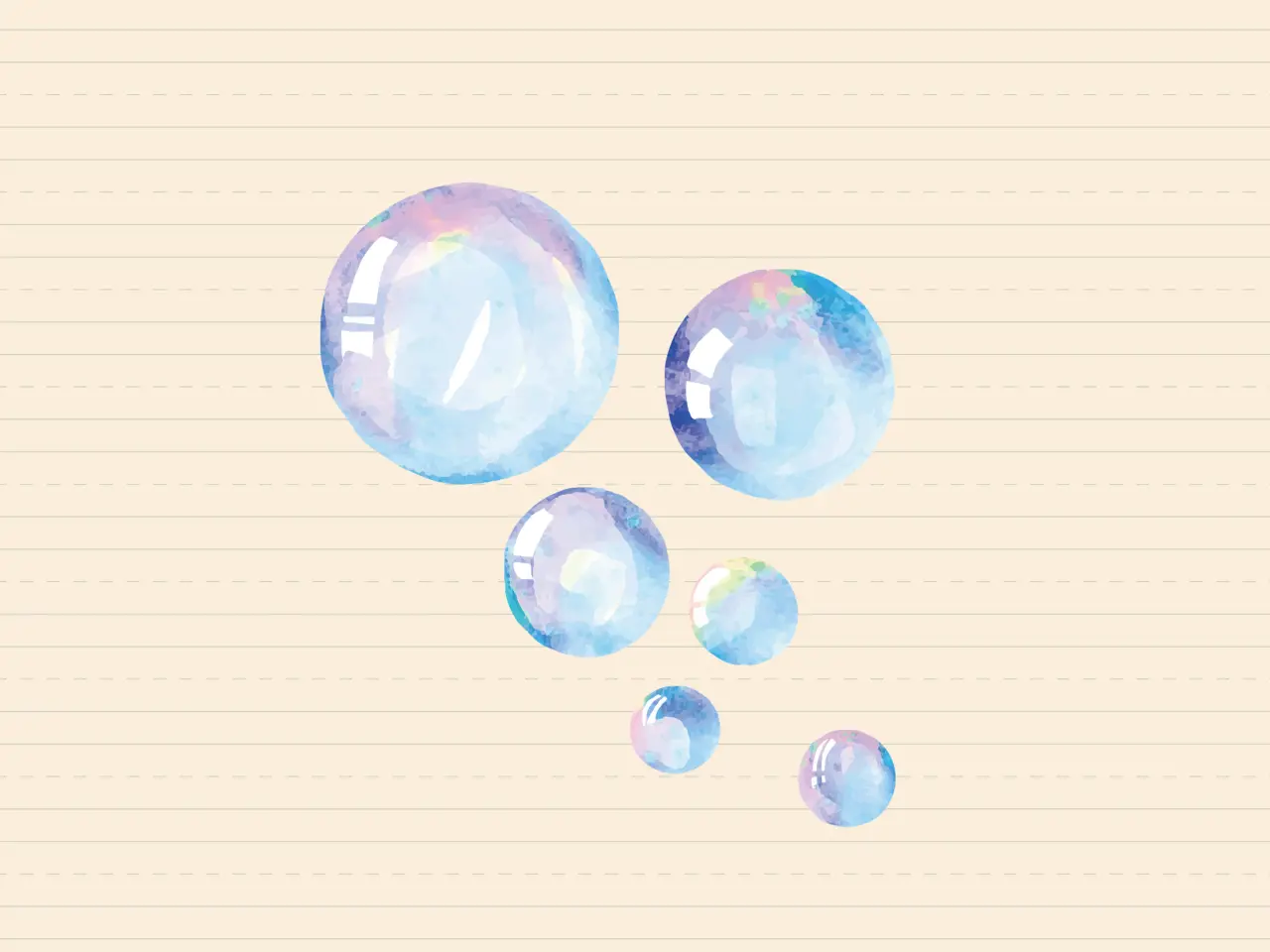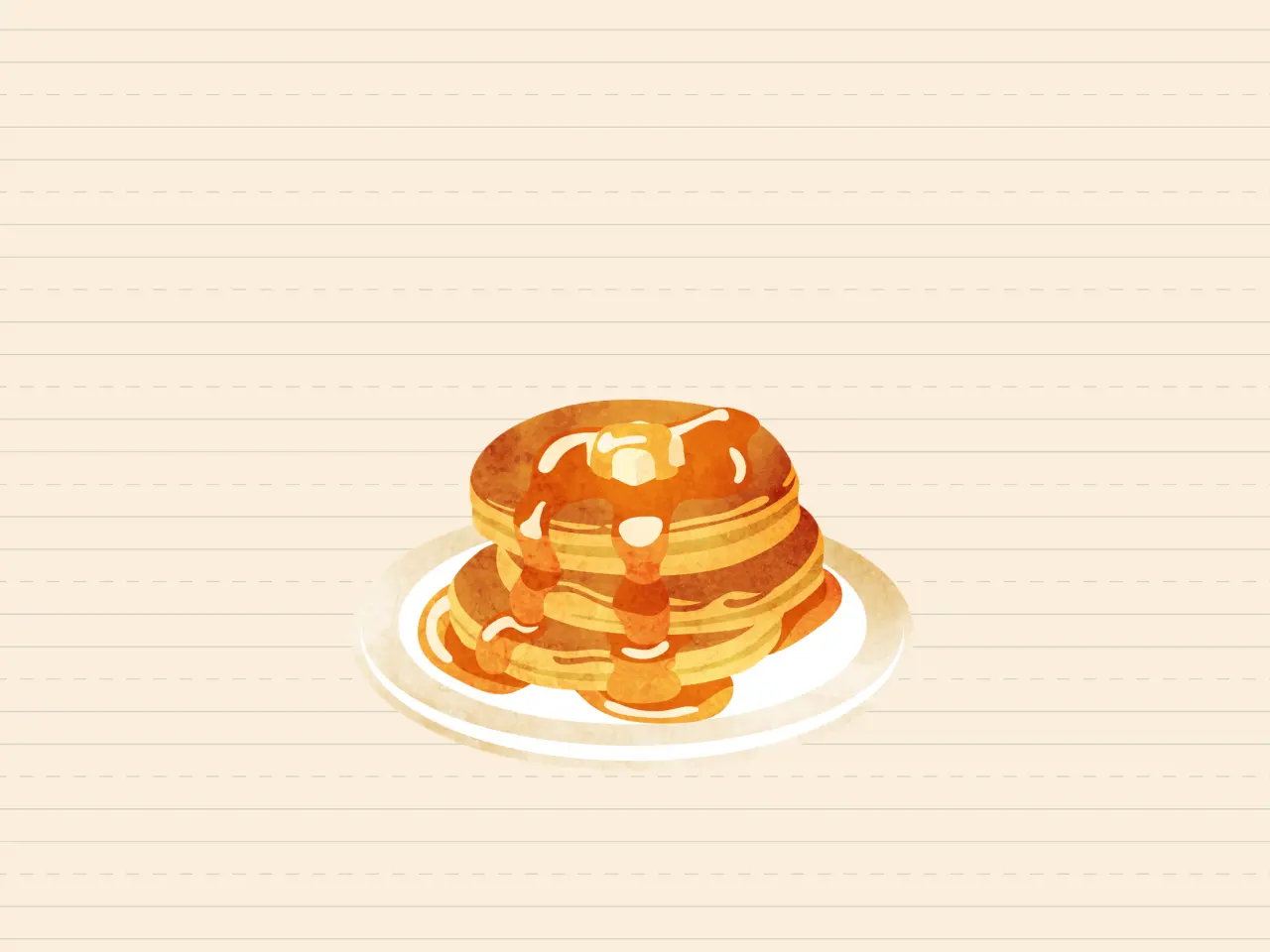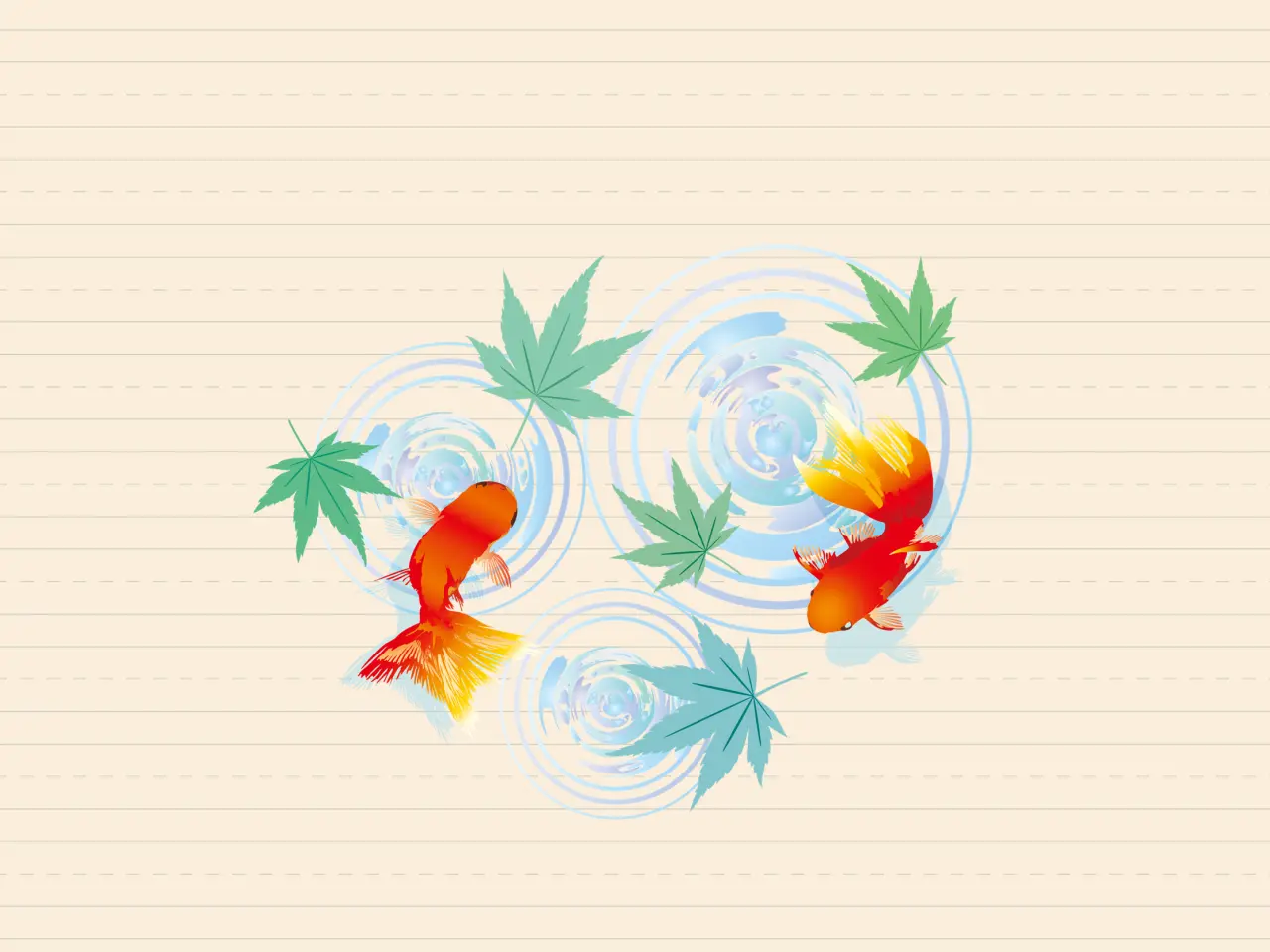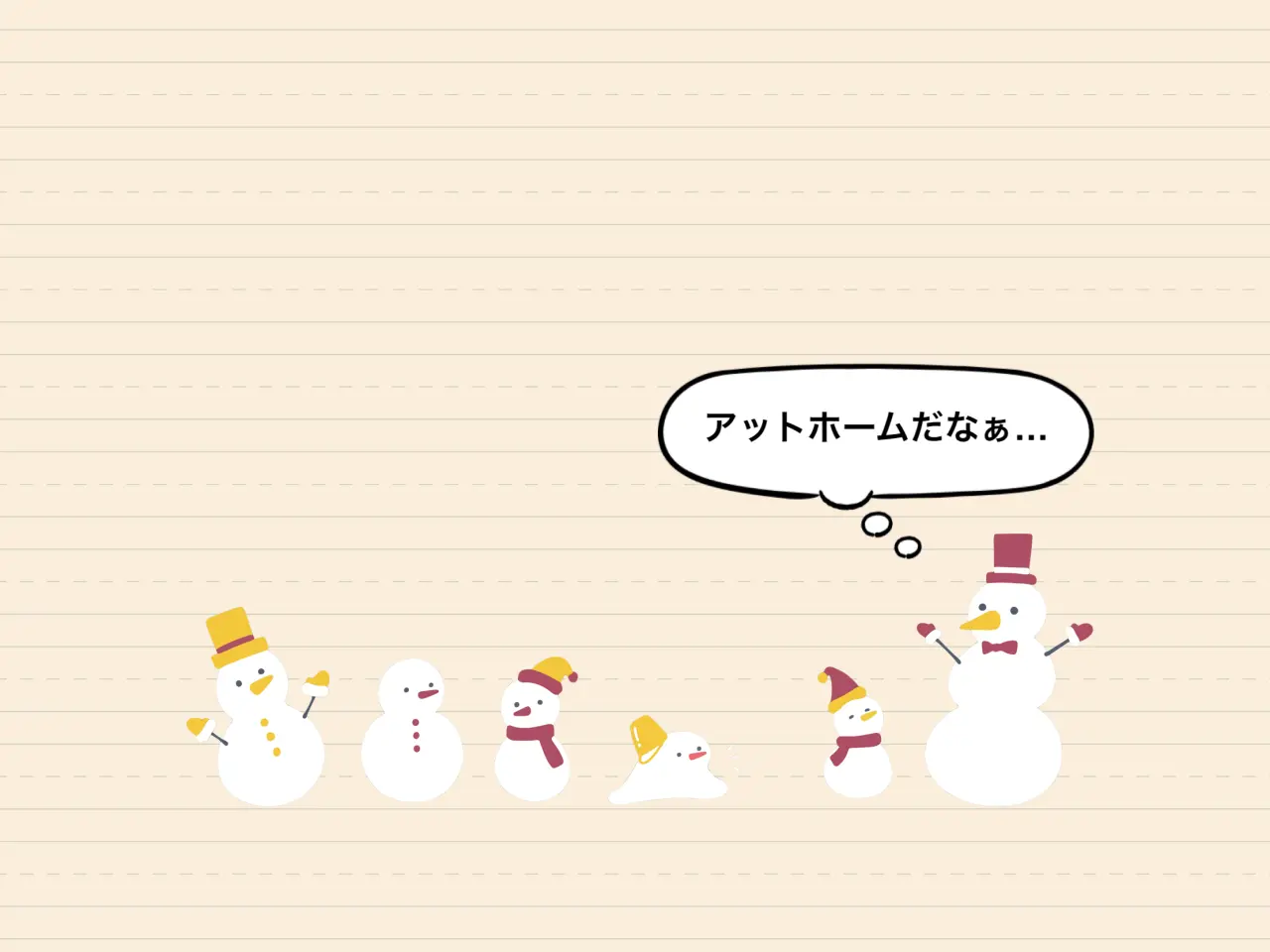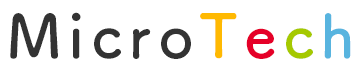【エンジニア連載】はじめに
先日「Mogicの人ってオノマトペを使うことが多いよね」という話になりました。そう言われるとたしかに。ざばっと、ぼんやり、ゆるっと、もやもや、がぎっと、ふわっと、しゃしゃっと、ごにょっと、などなど。感覚的な表現をみんなよく使ってそうです。
なんでだろうなぁと考えてみると、全部を言葉で定義しすぎないノリがあるのかもしれません。敢えて抽象的な状態 = ふわっとした状態のまま置いている感じでしょうか。受け手が好きに埋められる余白があるとも言えます。外の人が聞くと意味が分からず、はあ?となるかもしれません(笑)
この「ふわっとさせておく気風」は課題やフィードバックにも表れていると思います。課題も「こういうことをやってみて」と出されますが、具体的にどうしてみたいなことはほぼ指示されません。自分で調べて考えてみてねといった具合です。フィードバックも例えば「ここは深く考えられてない」とか「一見それっぽいけど心が抜けてる」みたいなことは言われますが、何をどうしたらいいかは特に言われないです。
学校での教わり方とは全然違うので、インターン生は戸惑うと思います。(僕はそうでした。)具体的なことを伝えられないので、言われた側はよく分からないモヤっとした気持ちになるんですよね。ただ不思議なもので、時間が経つとそのうち「あ、そういうことか」と腑に落ちる時がきます。それは数ヶ月だったり数年後だったり色々です。
自分にとってはこの教え方が自然なものになっているので、後輩に教える時も同じやり方でしたが、年末に読んだ本の内容で感覚が近いものがありました。
鈴木宏昭『私たちはどう学んでいるのか』
本の中で、教える対象を小さく分解してカリキュラムで教える方法だと木を見て森を見ずの状態になる。そうではなくて最初に全体像、目指すべきものを見せて探求してもらう、昔の徒弟制のような教育スタイルを見直してみてはどうかというくだりがありました。
細かく1つ1つ「教える」と、逆に本質的なことが見えなくなる例として、病院での事例が紹介されています。職員の方に患者さんへの対応チェックリストを渡してしまうと、リストに書かれてない状況で困っている患者さんは放置されてしまう傾向にあったようです。患者さんに寄り添うことが大切でそのためのチェックリストだったのに、具体的なTODOにだけ目がいき本質を見失ってしまったという教訓と捉えています。
個人的な感覚も似ていて、細かな方法論に目を奪われないで、全体の雰囲気やイメージをまるっと吸収してほしいので、ふわっとした課題やフィードバックにつながっていると思います。
この教育は長い目で見ると財産となる実感はあるのですが、一方で身につくまで時間がかかるので、途中で道に迷い挫折してしまう危険性もあると思っています。なので、教える側は時には具体的なことも混ぜて伝えたり、精神的なフォローをしたりと、相手の状態に応じてチューニングすることが大切なんだろうなと思いながら模索し続けます。